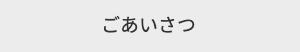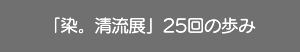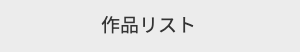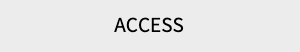「染・清流展」25回の歩み
「染・清流展」は今回で第25回展を迎えた。第1回展からこれまでの経緯を簡潔に辿ってみたい。
1991年2月5日から10日まで、京都市美術館で「第1回染・清流展」が開催された。
重鎮から中堅作家まで、染色工芸美術の第一線で活躍する作家30名が、この展覧会のために制作したパネル形式(屏風を含む)の新作を一堂に出品するという画期的な展覧会であった。とくに注目されたのは、日展(現代工芸美術家協会、日本新工芸家連盟)、新制作協会、モダンアート協会、新匠工芸会、日本工芸会、無所属など、当時、それぞれ溝のあった所属の垣根を超えて、各会派を代表する染色作家が、同じ展覧会に作品を出品するという、極めて稀有な展覧会であった点だ。
染・清流展の開催の目的は、大きく二つあった。日本で独自に発展した、国際的にも珍しい染めによる高度な芸術表現を広くアピールし、世界に発信させていこうということ。もう一つは、優れた染色作品をコレクションして、「染色のまち」京都に染色美術館を設立しようということであった。
染・清流展開催の母体となる清流会が1990年に発足し、その会長になった小澤淳二大松株式会社社長は、「私はこの企画を、一企業の単なる事業としてではなく、長期にわたる社会的文化事業として位置づけており、京都染色界の更なる発展の礎石にしたいと考えています」(第1回染・清流展カタログ)と明言し、本来的なメセナ(企業の芸術文化支援)としての姿勢を明確に打ち出している。
同展の理念に賛同し、その実現に尽力したのが、大阪大学名誉教授で美術評論家の木村重信、また日展理事で京都市立芸術大学名誉教授の佐野猛夫らであった。また清流会の事務局長に染色プロデューサーの山本六郎があたった。
染・清流展は、会員制をとらないこととされた。それは出品作家の固定化と階層化を避けるためだった。とはいえ、第1回に選ばれた作家は5回までは基本的に出品しており、2回目には新たに8名の作家が追加され、3回目にはさらに2名の作家が加えられて40名の出品作家となった。第4回展は、京都以外で初めて奈良そごう美術館でも開催された。
1996年の第6回展からは、選考方法の変更が行われ、出品者を固定せず、推薦者と選考委員による出品委嘱ということになった。1995年に最長老であった佐野猛夫が死去し、作家代表である推薦者5名(伊砂利彦、来野月乙、澁谷和子、三浦景生、皆川泰蔵)から推薦された候補者について、選考委員5名(小澤淳二、木村重信、福永重樹、藤慶之、山本六郎)が協議して、出品者を決めるという方式で、39名の作家が選ばれた。
1997年に開かれた第7回展は、京都市美術館で開催される京都展に加えて、10月10日から26日まで東京の目黒区美術館でも開催されることになった。東京展は、2001年の第11回展を除く2002年の第12回展まで5回開催された。東京展開催の実現は、同館の福永重樹館長の熱意と尽力によるところが大きい。
2001年の第11回展でより広い視点で出品作家を選ぶべく選考方法が見直される。選考委員5名(前述)による運営委員会を組織し、同委員会が毎年1回限りの推薦委員原則5名、特別推薦委員1名を選び、その回の出品作家の推薦を委嘱し、それに運営委員会が推薦する作家を加えて全体約30名を出品作家とするというものである。推薦委員には、学芸員、キュレーター、美術記者、編集者、教育者、美術家、工芸家などから選ばれた。推薦作家は、それまでの京都を中心にした作家だけではなく対象を全国規模に広げ、より幅広い人選を行うために、関西在住以外のメンバーも加え、各自原則5名を推薦し、それぞれの作家についてその推薦理由を明記するということにした。この運営方式は第14回展まで続く。
2005年に開催された第15回展では、新しい試みがなされた。染色分野以外の工芸作家4名(伊部京子、江里佐代子、久保田繁雄、服部峻昇)による各1人の推薦及び運営委員による推薦で出品作家を選んだこと。それと出品内容に課題を設定したことである。「自由制作」の作品と「衣裳」の両方の出品を条件とした。「衣裳」といっても「着物」を踏襲したものとは限らず、それぞれのアイデアで「現代のキモノ」を創作、同一作家の自由制作作品と「衣裳」が同じスペースに展示された。
2006年10月、染織商社が軒を連ねる室町通に面した明倫ビルに、当初からの構想であり念願であった染色専門ミュージアム「染・清流館」が開館した。京都芸術センターの北隣に位置し、畳敷きのミュージアムというユニークな設計である。設計を手掛けたのは、国立国会図書館関西館などの建築家として知られる陶器二三雄。展示室内照度は作品の褪色を防ぐため60ルクス以下で計画、そのため外部から展示室までのスムーズな暗順応に注意を払い、薄暗さを感じない空間づくりに配慮された。
館長には、木村重信が就任した。「染め」を世界に発信し国際語にしようと、染・清流館の欧文名をMUSÉE DE SOMÉ SEIRYUとフランス語で表記することになった。
第16回染・清流展は、2007年に染・清流館で開催された。運営委員(小澤淳二、木村重信、藤慶之、山本六郎)に選ばれた42名の作家の作品を、9月にPart1、10月にPart2として2回に分けて展示された。京都市美術館と較べて、染・清流館の展示スペースが広さの点で制限されたからである。この回以降、染・清流展は隔年で開催されることになった。
第16回展から2015年の20回展までは、木村重信、小澤淳二、山本六郎を中心に、ジャーナリスト、学芸員など固定されないメンバーが加わった運営委員による選考が行われた。この時期は、前期と後期の2会期制になって出品作家が増えた分、若い新鋭作家が選ばれる機会が増えたといえる。
2016年に事務局長の山本六郎が退任。元京都新聞記者でフリーライターの深萱真穂が、染・清流館のキュレーターになり、染・清流館で開催される展覧会などの企画運営を担当することになった。
2017年1月、当初から染・清流展を支え続けてきた染・清流館初代館長・木村重信が死去した。
2017年開催の第21回展では、いくつかの改革が行われた。運営委員を選考委員にし、メンバーは小澤淳二、河村亮、佐藤能史、辻喜代治、深萱真穂の5名であった。展覧会名が「第21回染・清流展ビエンナーレ2017」となった。「ビエンナーレ」は、2年に1回開催される美術展や芸術祭などに用いられるイタリア語である。さらに作家の人数が増えて小ぶりになりがちだった作品を、染・清流展発足当初の原点に立ち返り大きなスケールの作品も展示できるよう規定を変更し(高さ3m以内、横3.5m以内)、出品作家数を前回の44名から29名に少なくした。出品作家の選考方法は、選考委員の推薦作家の得票数を基本とし、無名でも優秀な作家を掬いあげるため、それぞれの選考委員に1名ずつ特別推薦枠を設け、そこで推薦された作家は得票に関係なく無条件に出品できることにした。
2018年1月に2代目館長として元京都国立近代美術館主任研究員、元池坊短期大学教授の加藤類子が就任した。
2021年の第23回染・清流展で、第1回目の開催から30周年を迎えた。その図録のあいさつの中で、会長の小澤淳二は「才能豊かな若い染色作家に参加していただくことで、染色美術界の将来を見据えたインキュベーター(培養器)の役割を、染・清流展及び染・清流館が果たしていくことができればとの思いを抱いております」と書いている。染色の世界を活性化していくためには、若い世代の作家を育成することが重要であり、その役割を染・清流展が担っていくことへの決意を表明したものだ。
2021年に加藤類子館長が退任、2022年にはキュレーターの深萱真穂が退任し、2023年1月に3代目館長として、大松株式会社社長の小澤達也が就任した。
「第25回染・清流展ビエンナーレ2025」には、選抜されたベテランから若手までの33名の作家が出品する。選考委員のメンバーは、小澤淳二、小澤達也、川嶋啓子、後藤結美子、佐藤能史、大長智広、辻喜代治、三村智哉の8名である。選ばれながら2024年に死去した澁谷和子の作品は、特別出品として前期、後期の2期を通して展示される。第1回染・清流展に出品した作家で今回出品する作家は、麻田脩二、井隼慶人、澁谷和子、兼先恵子、河田孝郎、髙谷光雄、田島征彦、中井貞次、福本繁樹、森口邦彦の10名となっている。
かつて20世紀のバブル期には、メセナの掛け声のもと企業の名前を冠した数多くの美術展やコンペティションが開かれた。しかし、そのほとんどがその後の景気後退の中で姿を消していった。これまでおよそ35年にわたって、染色美術の振興に力を尽くし、その魅力を世界に発信しようと、染・清流展を継続して開催し、今後のさらなる発展をめざして持続しようとする清流会の志は、きわめて意義あるものといえよう。