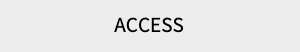風を主題にした小林祥晃
作家は興味関心や自身の経験や哲学から、インスピレーションを得てテーマを見極め、独自のコンセプトに基づいて個性を引き出すための作品づくりに取り組み、試行錯誤を繰り返す。
小林祥晃の場合、見極められたテーマは「風」である。鳥取砂丘を訪れた際に風が砂上に刻む風紋の景色に出会い、五感に響いた感動を自身のフィルターを通して心の風景として表現したいと考えるようになった。瞬時に変化していく風紋の造形は美しさとともに自然の力の偉大さ、厳しさ、儚さを想起させ小林の心を惹きつけた。風紋は、静謐なリズムとともに「生命さえも感じさせる力強い響き」を湛えて迫ってきたのである。
「風」というテーマは詩や文学、音楽でも度々取り上げられてきたが、小林は風に焦点を当てることで、作品を観る者が自然との繋がりを感じ、風や自然の流れとの一体感を味わえるような表現手法を模索し、「作品の前で自分で踊れるようにならないと」と、手や鉛筆でなぞりながら常に風の姿に心を留めてきた。
作品の特徴と作風の変遷をみていくと、1988年の初個展で風のシリーズが発表されたが、作品「嶰壑」(かいがく)の背景には実景が表されていた。1989年の「風濤」になると実景は姿を消し、その後の小林の作風を特徴づける撒き蠟の技法が現れるようになる。白い線の連続紋様が撒き蠟による紋様が結びついて、複雑な色彩を持ち、作品に奥行きと立体感をもたらす。一つ一つが思いの痕跡であるとともに、一際目を引く白い帯は、生命に関わるような神秘的な輝きを放つようになっていた。
1990年代に入ると国際展へ参加が増え、ドイツやオランダなどへの出品やワークショップを行う機会が訪れる。当時、ファイバーアートに比べると伝統的な蠟染め技法による平面作品は珍しかったが、小林の作品は現代的な表現力と日本の繊細で質の高い技術力によって、現代アートとして高く評価されるようになった。
しかし、2000年に差し掛かると転換期が訪れ、小林は新しいアプローチに挑戦する。いろいろなものが削ぎ落とされ、従来の撒き蠟や線紋様に代わって、抽象的な扉や壁、建物が画面に浮かび上がる。自然とは打って変わった街シリーズの登場である。色彩も一変し、静謐な色合いから鮮やかな赤や青、緑などが表れ、立体的な形態が矛盾する摩訶不思議な世界が広がった。この街シリーズも心象風景を表現したものであるが、例えば「想」(2000年)に見られるように、青や赤の棒線はそれぞれが人であり、複雑な軌跡を残している。空間と人との関係性を通して、時間の流れまでもが表現され、観る者の想像力を刺激する。この試みは、2004年には従来の風紋シリーズのパターンと結びついた「風の街・04」などの作品で展開され、2012年には、風紋シリーズに再び回帰する。
小林は心象風景を単なる絵画的イメージとして再現しているわけではない。染色技法の特性や制約を把握した上で、表現技法や素材の選択を慎重に重ねている。かつて「感性と技術のどちらが先行するか」と問われた際に、「工芸の場合、同位置にあるのではないか」と述べ、「実際に見たり触れてみて感動を憶え、その感動を作品に表現できるだけの感性と技術が伴わなければ、自分自身の納得のいく作品ができあがらない」と答えたことがある。彼の工芸観は、父や兄が金工や陶芸の作家という環境にあったからこそ、早くからものづくりの何たるかを肌感覚として体得していたのかもしれない。
蠟染めの手作業ならではの温かみを残し、蠟置きの技術と構図でシャープさを演出する。彼はしっとりしたやや光沢のある「ぬれ色」効果を引き出すために、綿から絹に変えるなど、作品や時代によって素材や染料などを常に見直してきた。大学時代に染めることに魅了され、その後着物づくりの経験で培かった独自の色彩感覚、長年にわたって技術、素材と真摯に対峙してきた姿勢があったからこそ、伝統的技法を駆使し現代性に溢れた作品の創出を可能にしてきたのだろう。