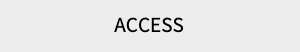撒蠟(まきろう)について
佐藤 能史 (キュレーター)
撒蠟は蠟染の多様な技法の中のひとつである。
蠟染は、蠟で防染して模様を染め表す染色技法で、古代にすでに代表的な染色技法「天平の三纈(さんけち)」の一つである﨟纈(ろうけち)として知られ、その染色品は正倉院宝物にも少なからず遺されている。9世紀末の遣唐使の廃止により、﨟纈の材料である蜜蠟が輸入できなくなったことで途絶し、明治末期に京都高等工芸学校の鶴巻鶴一が﨟纈を復興した。その後、様々な蠟染技法が開発され、染色の重要な技法となっている。
撒蠟は、刷毛などに溶融した蠟を含ませ、棒などに打ち付けることで蠟液を生地に細かい粒状に飛散させ、斑点状に付着させる技法である。斑点を平均に出すために、一度に蠟を撒かず、何度か繰り返して撒く。雪が舞うようなその染め上がりの表情から、蠟吹雪、蠟しぶきなどとも呼ばれる。
小林祥晃の場合、柔らかに揺らぐ線状を繰り返す筆による蠟描きと組み合わせることによって、自然のダイナミズムを感じさせる独自の表現へと昇華させた。