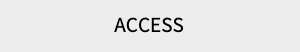ロウ染め文化の発信と小林作品
小林祥晃は1955年、金工家小林尚珉氏の三男として京都に生まれる。兄たちもそれぞれ金工・陶芸の分野で活動する工芸一家のなかで育っている。大学は金工科がある大阪芸大に進むが、そこで染織科を選ぶことになる。工芸の基礎課程の中で染織の特に、色が繊維に染みて変化する魅力に取りつかれた。それは今までの彼の環境では味わったことのない世界であった。当時大阪芸大染織科には、日本の伝統色研究の権威であり、天然染料の研究家である吉岡常雄が指導しており、小林は大学の4回生の時、特別に吉岡常雄研究所で研究生として、天然染料及び古代染織学などを研究している。そこで日本のロウ染文化を深く知ることになる。
大学卒業後は兄たちのように作家活動に入らず、職人として着物制作の世界で、自分の色彩感覚とロウ染めの技術を深めていった。しかしあまりにも厳しい環境のなかでの制作は、身体にも経済的にも大きな負担であった。そうした下積み生活を続けるなかで陶芸家の兄、英夫の助言と手助けによって徐々に作家活動へと入っていく。初めての作品発表は1988年で、大学卒業後10年が経ていた。作家としては遅い船出であったが、その後の小林の活動には目を見張るものがある。翌1989年には兄たちと同じ日展に初入選し、以後も連続入選を重ねていく。そして1990年代に入ると小林の視線は世界に向けられる。そのきっかけとなるのが、1992年京都で開催された第3回国際テキスタイル・コンペティション’92で、そこで入選を果たしている。さらに同年スイスで開催された第15回国際ローザンヌ・ビエンナーレ・コンテンポラリー・テキスタイル・アート展でも入選している。
染織界では60年代末から70年代を中心に、世界的に織から発展したファイバーアートが活発な展開を見せ、日本でも70年代中ごろには数多くの作家たちが国際的に活躍していた。その作品は平面的な織から出発し、徐々に立体的造形へ。そして“糸”を中心とした繊維素材を使い空間を意識した作品へと展開していく。その中心的な舞台となったのが、スイスのローザンヌで1962年から隔年で開催されてきた、国際ローザンヌ・タペストリー・ビエンナーレ展である。
やがて80年代に入ると、織の作家に加えて日本の染出身の作家も参入し、入選を果たすようになる。その作品は染める“布”に注目し、既存の布を作品展開するものであった。この80年代初めの作家たちを第一世代とあえて言うならば、80年代末から90年代同じ舞台に登場して来た小林等の染作家たちは、第二世代と呼べるだろう。その大きな違いは布による作品展開ではなく、“染”表現の作品を展開したことである。特に80年代以降、世界的にも日本独自の染表現作品は注目され、アメリカでは染作品をサーフェスデザインと呼び、研究会や展覧会が盛んに開催されるようになってきている。1994年には平安建都1200年記念として、清流会が中心となって京都市美術館で染・アート展が開催されている。そこで日本で初めて、サーフェスデザイン展が併設され、アメリカの染作品がまとめて紹介された。ちなみにこの公募展で小林は、優秀賞を受賞している。
小林は古くから伝わる日本のロウ染め文化の重要性を、早くから意識し作品制作すると共に、国外で発表を重ねるごとにその重要性を確信していった。そして90年代後半からは作品発表と共に、ロウ染め技術の公開や講演活動などをヨーロッパやアメリカにおいて積極的に行っている。(世界ローケツ会議の参加、招待発表・1999年ベルギー、2005年アメリカ他)。こうした成果は大学での教育にも反映され、さらに私塾開設へとつながっている。
ここで小林の作品を見ていこう。染は、布に染料が染みこんで発色する、極めて平面的な表現である。そして着物においては、絞りや刺繍技法、箔などを使って奥行きのある表現を追求してきた。しかし現代の染作品の多くはパネル状の平面である。小林は兄たちの立体表現と、自身の色彩表現に常にジレンマがあったように思われる。立体的表現への強いあこがれ、それが彼の作品制作を突き動かしているようにも思われる。そして作品の立体への試みを、染の表現と技術、そして表現の形式の両面から追求している。
1988年の最初の発表作品である「嶰壑」(かいがく)は、砂丘でヒントを得た風紋が造形化され、ロウ染めによってそれをストライプ状に曲線構成し、遠近感を持った表現作品となっている。90年代の世界的なコンペの挑戦作品では、曲線の画面構成に加えてさらに奥行きを増すために、撒ロウ技法、そしてぼかし技法を使い、複雑な色彩の構成作品となっている。その後の作品展開でも、彼の特徴となる多様な曲線表現と、撒ロウによって奥行きのある色彩表現を追求している。またボカシ技法は色彩を浮かび上がらせ、同時に白場を効果的に使った作品へと発展し、平面の染による立体的空間表現を深めている。
作品の表現形式では従来のパネル表現から、世界の表舞台で得た刺激と、日本の染作品の自信によって変化し、大型屏風形式からさらに多面体による立体表現作品も登場する。1992年の作品「響き」は5枚の変形屏風であるが、壁面からは30㎝ほど飛び出た半立体作品となっている。そして1996年の作品「Windy」に至っては、渦巻く風の表現と共に、その画面は金属によって波打つ半立体的な表現となっている。やがてそうした激しい形式は収まり、2000年の作品「想」では、作品はより大型化し(700㎝大)、パノラマのように鑑賞者を空間に包み込むような表現となっている。
日展作品では、限られた大きさでの表現となっているが、このような彼のさまざまな挑戦は自己の内部で昇華され、やがて代表作品として結実する。それが静かさと色彩の調和がとれた2012年の作品「風光」である。そしてこの作品は、日展において2回目の特選に選ばれることになる。
こうして小林は、ライバルでもある家族の作家環境とも呼応しながら、また長い下積み生活をバネとして、充実した創作活動に邁進してきた。しかし昨年2022年、更なる活躍を期待されながら惜しくも病没した。この展覧会のタイトル「風の記憶」は、展覧会の構想を練る折に兄の口から出たことばである。それは兄、英夫のそばを足早に通り過ぎ去った小林祥晃の記憶でもある。